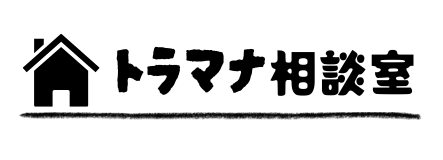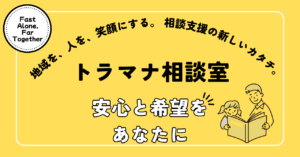障害福祉サービスの「困った!」をAIで解決!?
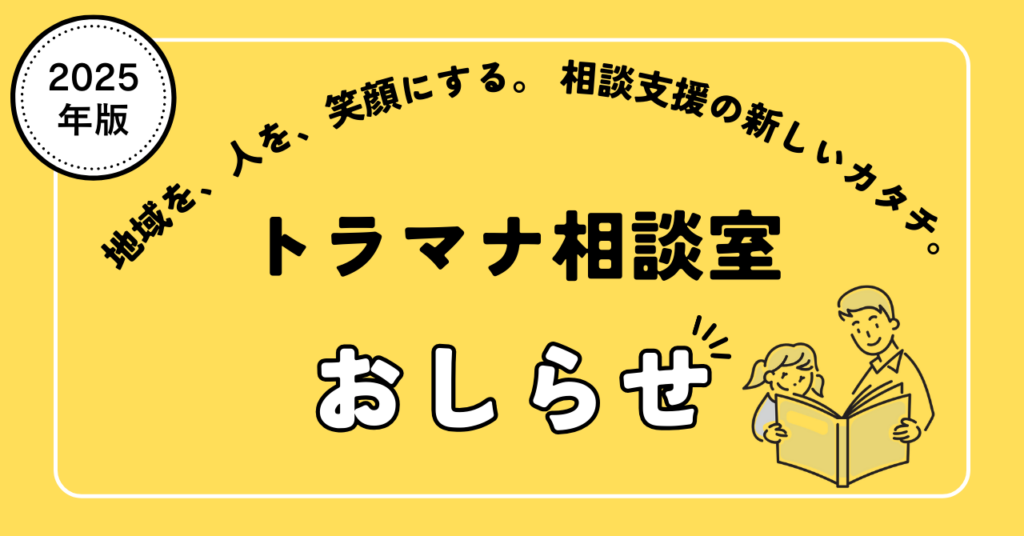
地域連携で未来を拓く相談支援の最前線
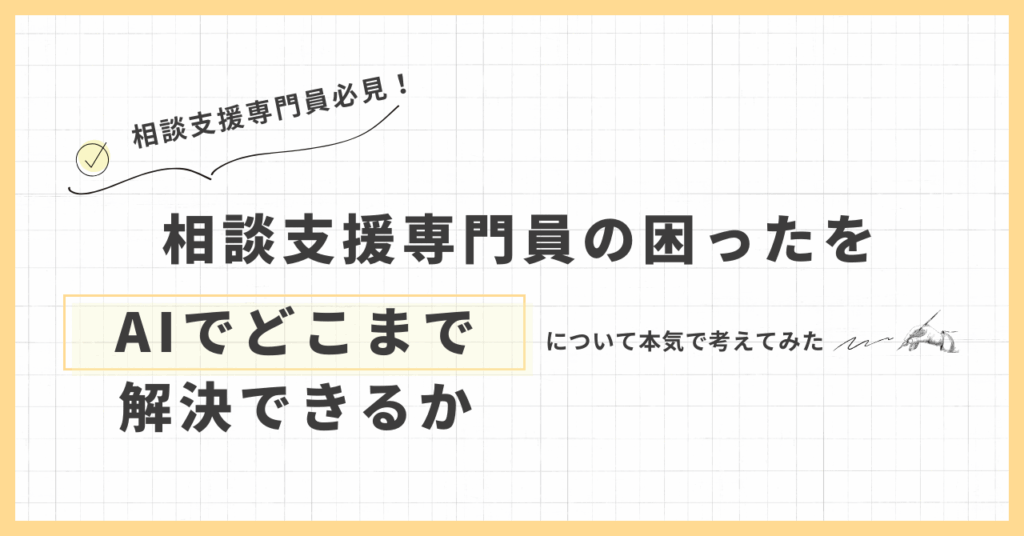
--------------------------------------------------------------------------------
日々の業務に奮闘する皆様へ
「相談支援専門員の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様です。
皆さんの熱い想いが、障害のある方お一人おひとりの『その人らしい暮らし』を支えていると、心から敬意を表します。」
しかし、その一方で、私たちは多くの課題に直面していることも事実です。
大阪府全体では、「利用者のニーズに対する相談支援専門員の数が追いついていない状況」が指摘されています。
「ひとり、あるいはふたり職場」が多く、「相談員同士が相談できない状況」や「相談員の育成に関しても事業所単位では限界がある」といった声も聞かれます。
さらに、多くの相談支援専門員が「書類などの作成に時間が取られ、実際の支援の時間が削られている」と感じており、
これが時にモチベーション低下の原因にもなっている現状があります。
「このような状況で、本当に質の高い支援を提供できているのだろうか?」と、自問自答することもあるかもしれません。
• 「計画相談」の重要性の再確認:
このような厳しい状況下でも、障害のある方が「自分らしく地域で生きていく」ために、「計画相談」は欠かせない、非常に重要な役割を担っています。
これは、単に福祉サービスを提供するだけでなく、
ご本人の「希望」や「困りごと」を丁寧に紐解き、その方らしい未来を描き、実現するための道筋を示す羅針盤なのです。
- からだは食べたものでつくられます。
- こころは聞いた言葉でつくられます。
- 未来は話した言葉でつくられます。
「障害者の権利擁護の観点に立って、生活ニーズと社会資源を適切に結びつける機能」を持ち、
何よりも「障害者の自己決定・自己選択を尊重する」ための援助方法が求められています。
第二回Hi-CoNet開催報告:地域における相談支援の質の向上を目指して
7月17日(木)に輝きプラザきらら5階セミナー室にて、第二回Hi-CoNet(枚方市相談支援事業所連絡会)が開催されました。
地域の相談支援専門員が一堂に会し、障がいのある方々へのより質の高い支援と地域共生社会の実現に向けた活発な議論が交わされました。
今回開催された連絡会では前半の勉強会にて「相談支援専門員として生成AIとどのように向き合っていくか」というテーマで
- 代表的な生成AIツールのご紹介
- 生成AIでできること
- 福祉現場での活用メリット
- 生成AIで変わる障害者支援の新しい形(書籍紹介)
- 具体的な活用例
- 実演デモ(プロンプト例)
- 導入時の注意点
- 始め方のステップ~小さくはじめて、大きく広げる~
- 生成AIをはじめとした現場でのICT活用を無料で学べるサイトの紹介

本会合は、障がい児者とその家族が地域で「その人らしい生活」を送るための重要な役割を担う相談支援専門員の資質向上と、地域連携の強化を目的としています。
新たな可能性:生成AIが拓く「計画相談」の未来
• 「計画相談」とは、何でしょう?
改めて、「計画相談」とは、障害福祉サービスや地域相談支援を利用するすべての障害のある方やそのご家族のために、相談支援専門員が中心となって、「サービス等利用計画(障がい児の場合は障害児支援利用計画)」を作成し、その後の継続的な支援を行うことを指します。
その目的は、「障害者が住み慣れた地域で、主体的に、共生・協働のもと生き活きと輝いて暮らせる社会を実現すること」にあります。
単にサービスを「手配する」のではなく、ご本人の「望む暮らし」を深く理解し、その実現に向けて、
福祉、保健、医療、教育、就労など多岐にわたるサービスや、近隣住民の助け合い、ボランティア活動といった
地域に眠る多様な社会資源(フォーマル・インフォーマル問わず)を組み合わせ、総合的な支援ネットワークを構築していく、
まさにオーダーメイドの支援計画なのです。
特に、ご本人が自身の意思を伝えにくい場合には、「意思決定支援」の視点から、情報提供や選択肢の整理を通じて、「自己決定を強化する」よう努めることが求められています。
「計画相談」の各プロセスとAI活用の可能性
この大切な「計画相談」は、ご本人との「出会い」から「別れ」まで、いくつかの段階を経て進められます。
ここでは、その主要なプロセスをご紹介しながら、AIがどのように私たちの業務を支える可能性を秘めているのか、考えてみましょう。
1. インテーク(出会いと問題の把握):
支援の第一歩は、ご本人やご家族との「出会い」です。「受理面接」「何をどうしていいかわからない」という混沌とした状況から、
「問題の把握」と「援助関係の形成」を行う大切なプロセスです。
「リラックスできる雰囲気や環境を整える」ことで、相談者自身が話しやすい状況を作り、傾聴や受容的な態度を通じて信頼関係(ラポール)を築くことが求められます。
AI活用の可能性:初回面談の記録を整理したり、過去の類似ケース(ただし個人情報は匿名化・特定されないように細心の注意を払う)の情報を素早く提示したりすることで、相談員が「対人援助技術」により集中できるよう支援するかもしれません。
2. アセスメント(現状とニーズの「見立て」):
ここでは、単に情報を集めるだけでなく、「利用者の生活全体を理解し、十分な意思疎通を図ることによって、ニーズを明らかにしていく」ことが重要です。
「本人さんの、どう思てはるんやろ……」という問いを常に持ち、表面的な訴えだけでなく、その人の「強み(ストレングス)」や、ご本人が当たり前と感じて気づいていない可能性に光を当てる視点が不可欠です。
「ニーズ整理票」のようなツールを活用し、本人の意思表明、客観的状況、支援者や周囲の判断を分けて考えることで、思考を可視化し、より深く「見立て」ていきます。
AI活用の可能性:膨大な情報からの「情報収集」や「整理・分析」、また、得られた事実に基づいた「見立て(評価)」の補助として、客観的な視点を提供できる可能性があります。
例えば、アセスメントシートの記述補助や、情報から潜在的なニーズを推測するヒントを提供するなど、相談員がより本質的な「見立て」に集中できるようになります。
3. プランニング(夢や希望を形にする「手立て」):
アセスメントで明らかになったニーズやご本人の「夢・希望」を踏まえ、「具体的な方法を選定し、支援計画を策定する」プロセスです。
「サービス等利用計画」では、公的サービスだけでなく、近隣住民やボランティア活動、趣味の集まりなど、地域にある
「インフォーマルな社会資源」も組み合わせ、多角的な支援ネットワークを形成することが大切です。
「共通の目標」「役割分担」「情報共有」を明確にし、関係機関がチームとして協働するための基盤を整えます。
AI活用の可能性:過去の計画や社会資源の情報から、利用者のニーズに合ったサービス組み合わせの提案を生成したり、計画書のドラフト作成を支援してもらうことで、作成時間の短縮に貢献できるでしょう。
4. インターベンション(支援の実施と介入):
策定された計画を実行に移す段階です。面接による直接的な働きかけに加え、社会資源を効果的に活用する間接的な支援も行われます。
「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」を目指し、様々な関係機関との連携が不可欠です。
AI活用の可能性:支援進捗の管理や、次に必要な支援内容のリマインダーとして活用できるかもしれません。
5. モニタリング(経過の「見直し」と調整):
計画通りに支援が展開されているか、「計画された支援が効果をあげているか」、そして「新たなニーズが出てきていないか」を定期的に確認する、継続的な見守りのプロセスです。
利用者の居宅等を訪問して面接を行い、サービス提供事業者や他の専門職とも連携して状況を確認し、必要に応じて「支援目標や支援計画の見直し(再アセスメント)」を行います。
AI活用の可能性:モニタリング結果の記録を効率化したり、入力された情報から「変化の兆候」を分析し、「計画変更の必要性」を早期に示唆することで、迅速な対応を支援する可能性があります。
6. エバリュエーション(支援の「振り返り」と評価):
支援全体を見つめ直し、その有効性や効率性を総合的に判断するプロセスです。
「目標の達成」「問題の解決・緩和」「生活の改善」などの視点から効果測定を行い、支援者が一方的な自己満足にならないよう、客観的に自己を見つめることが大切です。
AI活用の可能性:データに基づいた評価レポートの自動生成や、長期的な視点での支援効果分析をサポートすることで、より「根拠に基づいた支援の改善(エビデンス・ベースド・サポート)」に役立つかもしれません。
7. ターミネーション(支援の「別れ」と次へのつながり):
問題解決の過程を振り返り、将来的に同様の問題に直面した際に、ご自身で解決が図れるよう支援を終結させるプロセスです。
残された課題の確認や、再利用の可能性についても伝えるなど、次へのステップを視野に入れた支援が求められます。
AI活用の可能性:終結後のフォローアッププランの作成や、関連情報の提供を支援できるかもしれません。
★ AI導入の注意点:
ただし、AIは万能ではありません。AIが生成する情報は、あくまで参考です。「AIの回答は必ず人間が確認」「人間による最終チェック」が不可欠です 。
特に「個人を特定できる情報は入力しない」、「必ず匿名化して使用」すること、そして「段階的な導入」と「組織内ルール」の策定が重要であることを強調します 。
ご本人のプライバシー保護と人権尊重は、何よりも優先されるべきです。
AIだけではできないこと:人のつながり、地域との協働
• Hi-CoNetの真価:
「AIはあくまで強力なツールであり、最も大切なのは、私たち相談支援専門員と、地域に暮らす皆様、そして他の支援機関との『人のつながり』と『温かい支援』であることは変わりません。」と述べ、人間中心の支援の重要性を再確認します。
枚方市では、「地域全体で障害者を支えるために必要となる施策について定期的に議論」を行う「枚方市自立支援協議会」を設置しています。
この協議会は、「地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る」ための重要な場であり、「地域の相談支援の拠点」として機能する「基幹相談支援センター」がその中心的な役割を担っています。
実際、「地域で協働する」ことで、「一人相談員、兼務相談員などによる業務上の不安を減らす」ことができ、「困難な事例を抱え込みやすい小規模事業所が、不得意さを感じる経験の浅い分野のケースについて、事例検討やグループスーパービジョンを通じて、知識・スキルを向上する機会」を持つことができます。
このネットワークは、地域課題の発見と解決、そして私たち相談支援専門員のスキルアップと心の支えとなる、かけがえのないものです。
AI導入の検討も、こうした「質の向上」と「相互の支え合い」の延長線上にあります。
地域連携の呼びかけ:皆様の力を合わせて、より良い未来を
• 参加への呼びかけ:
「私たちHi-CoNetは、これからも、このような学びの場を継続し、相談支援専門員の皆様が自信を持って、より質の高い支援を提供できるよう、様々な取り組みを進めていきたいと考えています。」
「枚方市だけでなく、近隣の地域の事業所の皆様とも、ぜひこのネットワークを広げ、共に学び、支え合える関係を築いていきたいと願っています。」
「地域において継続的かつ適切に相談支援するためには、相談支援専門員の人材確保及び経験の浅い相談支援専門員へのサポート体制の構築、個々の相談支援専門員の資質向上が求められています」
「顔の見える関係」を築き、地域全体の支援力を底上げしていくために、皆様の積極的なご参加を心よりお待ちしています。
「AIという新たな技術も活用しながら、私たち人間の温かい心を大切にした相談支援の未来を、一緒に創っていきませんか?」
• イベント情報の告知:
次回のHi-CoNet(枚方市相談支援事業所連絡会)は視察研修を予定しています。研修先と調整中ですが8月中に実施を考えています。
お問い合わせやお申し込みはトラマナ相談室で受け付けています。
「お問い合わせだけでも大歓迎です。どんなことでも、お気軽にご連絡ください。」
トラマナ相談室
枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら6階インキュベートルーム11号室
電話 072-817-9580
FAX 072-817-95781
メール toramana.se@gmail.com